今回は、「現場監督に必要なスキル・知識とは何か?」というテーマでお話しします。
学校では施工管理や建築理論を学びますが、現場ではそれだけでは足りません。
現場監督として25年間働いてきた経験から、現場で本当に求められる力について、現場目線でお伝えします。
建築施工の基礎知識
建築施工をやって必要だなと感じる知識について説明します。
まずは絶対的に必要もの
①施工に関する知識
・施工方法の知識(専門工事会社が詳しい)
・施工計画の知識(ゼネコン会社の技術系の人が詳しい)
・施工の仕様・基準の知識(官庁営繕:公共建築工事標準仕様書や建築工事監理指針に書いてある)
これらは徐々に覚えていけばいいのですが、誰に聞けばいいか、どの本に書いてあるかを知っておけばいざというときに困りません。
②建設業法、労働安全衛生法
本来施工管理としてはこの2つの法律の内容は完璧に理解しておかなければいけないのでしょうが、これもなんとなく理解していて、これを調べればわかるというものを持っておけばいいと思います。
WEBで検索が一番早いですが、随時更新されていくので、最新の情報か見分ける力が必要です。
③建築基準法、消防法
法規は学校でも習うと思いますが、基本的なことは本当に大事だと思います。建築基準法などの法規制に関しては設計者がプロフェッショナルで知識が豊富なので、わからないことは聞けば大抵のことは調べて教えてくれます。しかし施工者として設計者や発注者へ提案や助言をする際、建物の基礎とも言える法律を無視した発言はできません。ですので、この内容はある程度理解しておくべきです。
④学校で習う知識
構造を理解していれば強いです。簡単な力学だけでもいいのですが、結構使える場面が多々あります。
例えば足場の強度計算や型枠支保工の計算、外壁の耐風圧計算など、活躍する場面がたくさんあります。ここは私も真面目にやっておけばよかったなと後悔するところです。
その他、設備や建築計画、歴史など一般的な知識として持っていれば、発注者や設計者・監理者と話すときに役立ちます。
あと感じるのがゼネコンの現場監督は、日本の建築文化に疎い人が多いです。仕事柄コンクリートや鉄骨を扱うことが多いので仕方ないところはありますが、日本の素晴らしい建築史に触れてみるのも良い勉強になると思います。
以上が私があったほうが良いと思う知識ですが、どれも深く覚える必要はなく、何を調べればよいか、誰に聞けばよいかをわかっていることが大事です。
必要な場面で調べ、実践で使うことの繰り返しで確実に身につきます。
広く浅く知識をつけるには、施工管理技士や建築士の資格取得の勉強が非常に良い機会だと思いますし、こういった教材は本当によくまとめられていますので知識の整理に最適です。
コミュニケーション力
現場監督は、職人さん、協力会社、設計者、発注者など、さまざまな立場の人たちをつなぐ役割です。
重要なのは「伝える力」と「聞く力」。
相手の立場に立ち、話をじっくり聞きながら、的確に情報を伝えることで、現場の信頼関係が築かれます。皆さんプロの集まりなので結構話を聞いてくれません。いかに短時間で情報を伝えるか。言葉だけではなく書面で伝える方法も有効です。
よく高圧的に「怒る」態度を取る人がいますが、「一緒に考えよう」と言う対話型ほうが、現場はうまく回ります。たまには「怒る」ということも必要ですが、アンガーマネジメントは大切です。
段取り力(工程管理)
「段取り八分、仕事二分」と言われる通り、段取りが現場の成否を左右します。
複数の業者、材料、天候、検査…これらを正確に組み合わせ、スムーズな流れを作る力が必要です。
ただ、こういった仕事の段取りをうまく作るためには、各工事の施工計画が重要になってきます。
施工計画とは、例えば基礎工事なら、敷地条件によって掘削の進め方、重機の台数の検討、残土の搬出台数、基礎躯体工事の工区割り、作業員の人数等を検討し、計画を作ることです。これがあってこそ工程が作られ、日々の工事の段取りができます。(施工計画についてはまた具体的な内容を書きたいと思います)
経験が浅いうちは、先輩の段取りをまねる・工程表を毎日見返す・翌日の作業を頭の中でシミュレーションするといった積み重ねが大きな力になります。
安全意識と観察力と感性
現場で事故が起これば、工事は一瞬で止まります。
安全管理は現場監督にとって最重要の業務です。決して疎かにしてはいけません。
ポイントは、「大丈夫だろう」ではなく「もしかしたら」を探す目を持つこと。
足場、工具、作業姿勢など、小さなリスクも見逃さず、日常的に声かけ・確認を行うことが、現場の安全文化につながり、自身の安全の感性を高めることにもつながります。
図面を読む力
図面を理解することは現場監督の基本です。
最初のうちは現場で作らている施工図を理解しましょう。
単に記号を読むだけではなく、「どう施工するか」「注意点はどこか」「他業種との取り合いはどうなるか」をイメージできることが大切です。
施工図の意味がわかってきたら、該当する箇所の設計図を見てみましょう。現場と施工図と設計図を見比べることで、なぜこの線、記号、寸法が書かれているかわかってくると思います。
とにかく現場では、図面を持って、図面と実物を照らし合わせながら確認するのがおすすめです。
より理解が深まってきたら、先輩に言って図面チェックをさせてもらいましょう。急激に図面を読む力がレベルアップしていきます。
忍耐力と冷静さ
最後に精神論に近くなりますが、忍耐力と冷静さも大事な要素です。
現場は常に予定通りには進みません。
天候、材料トラブル、人員不足など、イレギュラーな事態は日常茶飯事です。
そんなときこそ、焦らず冷静に状況を整理し、優先順位を立てて対処する力が求められます。
トラブル対応を一つずつ乗り越えた経験が、強い現場監督を育てます。
【まとめ】
現場監督に必要なのは、単なる知識や技術だけではありません。
現場で人と関わり、問題に直面しながら身につける、“人間力”と“現場感覚”も大切な武器になります。
最初は誰でも不安で、失敗もたくさんするものです。
でもその一つひとつが、スキルとなり、知識となり、やがて自信に変わっていきます。
このブログを通して、「現場でしか学べないこと」の大切さを少しでも伝えられれば嬉しいです。
【次回予告】
次回は、「現場監督にとって“信頼される存在”になるために大切なこと」というテーマで、
現場での信頼の築き方や、私が心がけていたことについてお話しします。どうぞお楽しみに!
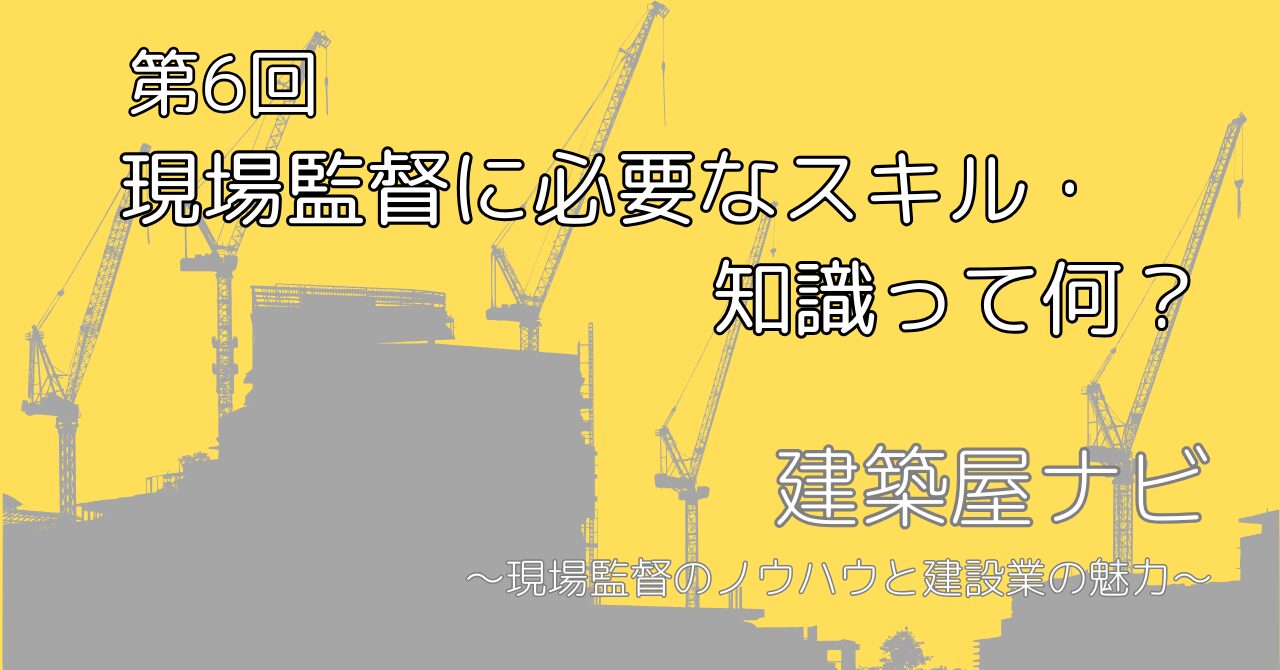
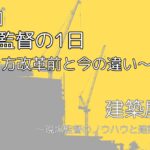
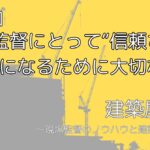
コメント