こんにちは、現場監督引退です。
私はこれまで、ゼネコンの現場監督として25年間、さまざまな現場に携わってきました。現場代理人(所長)としても12年の経験があり、多くの若手技術者と一緒に現場を動かしてきました。
若手の育成は、現場を円滑に進めるためだけでなく、業界の未来をつくる大切な仕事です。今回は、若手育成の考え方や実践してきたことを、少しお話ししてみたいと思います。
昔と今では「覚え方」が変わった
今の若手を育てる中で強く感じるのは、働き方そのものが変わっているということです。
私が若手だった頃は、現場に朝早くから夜遅くまで張り付いて、寝る間を惜しんで仕事を覚える、というのが当たり前でした。いわゆる「現場で盗め」「見て覚えろ」の時代です。
でも、今は働き方改革によって労働時間が大きく制限されています。
若手が仕事に費やせる時間は限られ、その短い時間で効率よく学ばなければいけない時代になったのです。
この環境で、「昔はこうだった」「俺たちの時代はもっと厳しかった」と言っても意味がありません。今の若手に合った“新しい教え方”にアップデートすることが、ベテランの役割だと思っています。
「言葉にして伝える」が基本
短時間で成長させるには、漫然とした指導では足りません。
「なぜこの作業をするのか」「この判断の根拠は何か」――経験則をできる限り“言葉”で“具体的”に伝える努力が必要です。
たとえば、安全管理ひとつ取っても、「ここに手すりが必要だ」とだけ言うのではなく、
「作業床が2m以上の場所は手すりが必要だと安衛法で決められている」と、理由を説明することで、理解の深さがまったく違ってきます。
“見て覚えろ”の時代から、“言葉で伝える”時代へ。
これは私たちベテラン世代にとっての大きな転換点です。
「任せてみる」ことが成長の一歩
指導で大切なのは、“教える”より“任せる”という姿勢です。
私が所長になってから意識したのは、若手にも早い段階で仕事を「任せてみる」こと。
もちろん最初から完璧にできるはずはありません。でも、自分で考えて動いた経験は、なによりの成長の糧になります。
任せた仕事には、時々進捗確認し、方向性が間違っていないか確認することです。また、最後に必ず「なぜこうしたのか」を聞いてあげて、うまくいかなかった点があれば一緒に振り返る。これを地道に繰り返すことで、考える力が育ち、判断力も磨かれていきます。
伝えるときこそ「理由」と「期待」を伝える
現場ではミスもありますし、指摘しなければならないことも当然あります。
ただ、私はいつも「失敗を叱る」のではなく「伝え方」に気をつけることを意識してきました。
感情的に伝えてしまうと、若手は委縮してしまい、動きづらくなります。
まずは何がダメなのか「理由」を明確に伝え、「君ならできると思っているこそ伝えているんだ」と、「期待」を伝えることで、相手の受け取り方は全然違います。
今の若手は特に、「納得感」や「意味」を大事にする傾向があります。
一方的な指摘ではなく、対話としての伝え方が大切です。
若手を育てることは、自分の仕事を広げること
私もベテランの皆さんと同じく自分で色々と処理してしまい、任せるということがなかなかできませんでした。しかし、今の労働時間が制約されている中では、一人でできることは限られます。こういった状況下では、一人ひとりが仕事に責任を持ってもらい、「自分がいなくても回る状態」を作らなくてはいけないと痛感しました。
それは裏を返せば、「人を育てて任せる」ことに他なりません。
若手が育てば、自分がやるべき判断業務や管理業務に集中できますし、現場全体の生産性も上がります。
つまり、人を育てることは、巡り巡って自分のためにもなる。
そしてそれが現場全体、ひいては建設業界全体の未来につながっていくと信じています。
若手は若手なりに結構考えて仕事をしています。信じて任せてみましょう。
最後に:一緒に成長する関係をつくる
若手を育てるというのは、上から目線で教えるだけの関係ではなく、ともに成長する“パートナー”のような関係を築くことだと思います。教えているつもりが、逆に気づかされることも多くありましたし、若手の発想や感性に学ばされることもありました。
だからこそ、育てるという行為は、現場監督としての“最後の仕事”ではなく、自分を育て直す機会でもあるのだと思います。
次回予告
次回は「現場監督と“お金の話”〜原価管理のリアル〜」というテーマで、
現場を運営するうえで避けて通れない“お金”の管理についてお話しします。
設計・施工だけでなく、利益をどう守るかという視点はとても大切ですので、ぜひご覧ください。
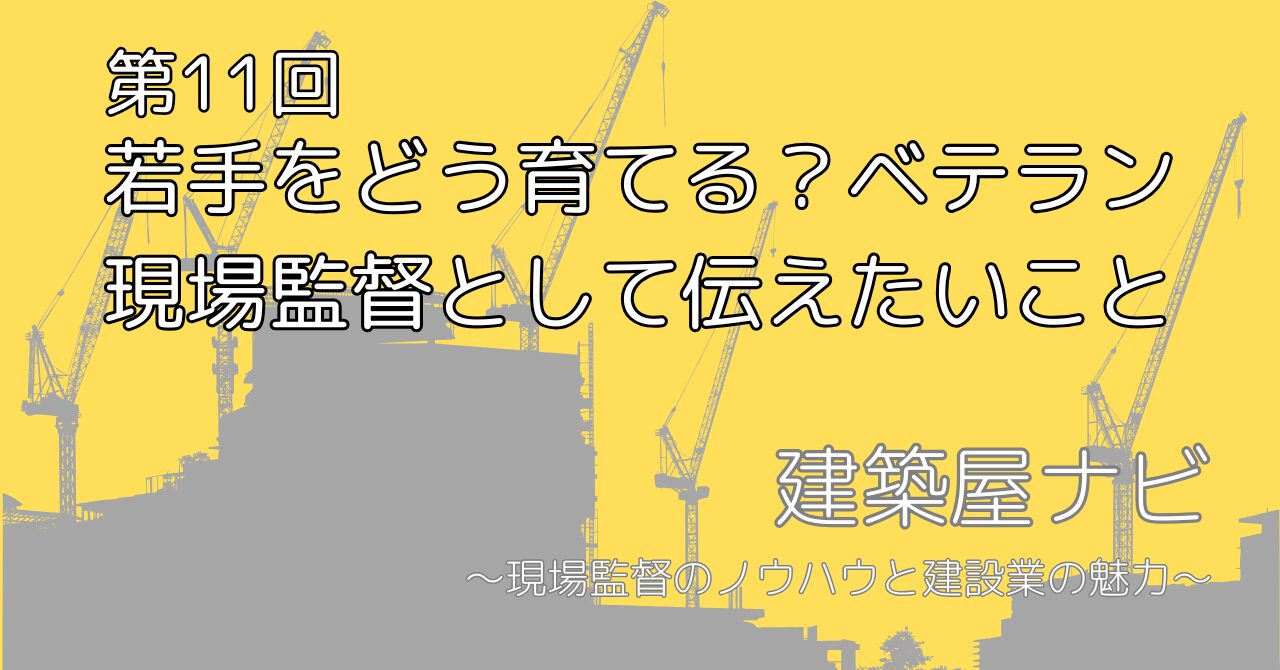
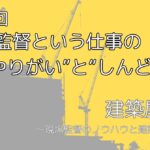

コメント